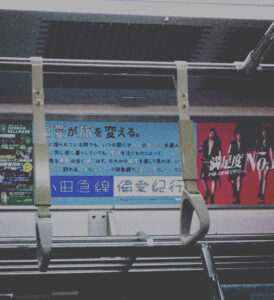LITERACY 越境のロマンス

大学時代
先輩の研究テーマで初めて「越境文学」という言葉を知った。
先輩は翻訳の角度から切り口を入れているが、訳者のワタシと作者の私はオーバーラップしてるか否か
セミナーでは、小さい時海外に移住した日本人作家が書いた小説をテーマにした時もある。
今、「越境」はECサイトなどに用いられるが、やはりこの言葉を聞いた瞬間、私の頭に、行間の空白、国境の狭間を行き来し、もがく作家の姿が思い浮かぶ。
どちらにも縛られていないと同時に
どちらにも属していない漂泊感
自分って何者?
この問いにロマンと哀愁を感じる
言葉と認識のぶつかりから生まれた一連の章節
人より跨ぐ範囲が広いだけに、心の葛藤も倍増する
もちろん創作する楽しさもその分多く味わえる
自分を消すか生かすか
翻訳者がいてもいなくても、すでにこの矛盾が最初から潜んでいるように思う。
差異を行き来する越境
これからの時代のトレンドかもしれないが
それが「和」の到来をも意味してる。
★
「越境」
大學時期,因學姐的研究題目才第一次知道「越境文學」這個領域。
學姐從翻譯者的角度探討這個命題,譯者的造詣是否間接影響了原作者的思維
除此之外,在課堂上我們也有討論過其他主題,從小生長在國外的日本人,他們的日語跟土生土長的日本人是否有別?
現在「越境」多半是跟線上EC網站一同出現,但當我聽到這詞,我腦海浮現的還是糾結在字裡行間,漂蕩在國境邊界的作家身影。
不拘束於哪裡的自由卻也注定沒有歸屬的漂浪
「我是誰?」
作家的這一自問,總讓我思緒奔馳,感動與哀愁。
從語言與認知的激盪而誕生出來的作品,當作家跨足的世界比一般人多的時候,也許內心的苦悶和掙扎也會成比例增多,但那也同時意謂著將不匱乏創作的樂趣。
「我」的存在,該扼死或放飛,這個矛盾從一開始就存在,有無譯者的介入似乎都不再重要。
穿越各個差異的「越境」
也許是接下來的時代趨勢
我們將更加矛盾卻融和。
Sony A7ⅱ